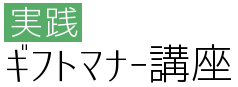社会人としてのマナーが求められる服装
学生から社会人になるときに苦労することの一つに服選びがあります。
学生時代は公的な行事に自分主体で出席するという機会がほとんどなく、また中高生であれば制服がそのまま正装として扱われるので特に服装のTPOについて厳しく求められるということはありません。
しかし社会人ということになると、公的な場に出るときには必ずドレスコードが守れているかということが厳しくチェックされていきます。
その象徴的な出来事が就職活動ですが、就職活動でどのような服装や振る舞いをしているかにより企業はその人が「社会的な一般常識を理解しているか」ということをはかっていきます。
最も厳しく服装についてのルールやマナーが求められるのは冠婚葬祭の場で、きちんと常識的な服装をしているかということで社会人としての評価を受けることになります。
ただマナーは時代によって少しずつ変遷していくものですし、冠婚葬祭というイベントの意味も変化してきていることから昔ほど厳しく守ることは求められなくなってはきているようです。
しかしながらだからといって普段と同じようなファッションで公的な場所に出かけるというのは、自分自身の品位を落とすだけでなく、その行事を主催する人に大変無礼な行為をすることにつながりますので、最低限度はルールに沿った服装を着ていくようにしたいところです。
冠婚葬祭用の服装のことを「フォーマルスーツ」と言い、基本的には複数の場面で同じものを着用してもよいとされています。
「フォーマルスーツ」というのは言い換えると「格式の高い場所で着用する正式な服装」のことで、結婚式やセレモニー、葬儀の時のほか、授賞式や格式のある場所や人との食事会でも着用するのが一般的です。
ただしフォーマルスーツは一種類ではなく、その中にも格式の段階があります。
わかりやすいのが男性用のスーツで、「正礼装」「準礼装」「略礼装」という三段階に分けられます。
具体的には男性の場合の正礼装はモーニングコート(午後6時までの式)やイブニングコート(午後6時以降の式)で、準礼装はディレクタースーツやタキシードといったものとなります。
略礼装はブラックスーツであればよいとされており、こちらはどういった式であるかによりやや柔らかく解釈をされます。
どのランクのものを着用するかは自身がホスト・ゲストのどちらであるか、またはその式自体の格式によって異なってきます。
ビジネススーツはその場に応じて使い分けする
冠婚葬祭については数多くのマナー本が出版されているのでわかりやすいですが、ビジネスにおいては必ずこうではなくてはいけないということはありません。
業界や社風など所属する場所により服装のマナーは大きく変わってきます。