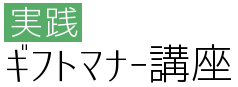のしの種類
のしというのは、「贈答品に対する思い」によって変化するもので、今では以下のようなのしの種類が存在します。
のしの種類その1ですが、のしには「紅白蝶結び」という祝いのしが存在します。
主に、「一般的な祝辞で用いられることが多いのし」ということで、今でも良く見かけるのしとして知られています。
「お中元、お歳暮」にも使われていますが、簡単に結び直せる蝶結びの水引が特徴的で、こちらは簡単に結び直せる水引が、「何度でも繰り返したい」という意味合いで使われているのです。
仲が良い相手と、これからも仲の良いままでありたい・・・という、日本人独自の繊細な気持ちが水引に表されているということです。
他にも、「結び切り」という祝いのしも存在します。
結び切りは、「重ねて起きて欲しくない」という思いが込められているので、「快気祝い、お見舞い」などで使用するのしです。
のしの中には、結び切りのようにこれから先の健康、幸運を願って使われるものも存在しますので、状況によってのしが変化するというのも、他では見られないのしだけの特徴と言えるでしょう。
のしの中には、「お悔やみ事」で使用される「仏のし」というのしも存在します。
お悔やみ事で見かけるのしなのですが、仏のしは「黒白の色が使用されている」という特徴があります。
それと、おめでたい時に使用する「熨斗」は、結び切りの時と同じで使用されておらず、仏のしはお悔やみ事だけでなく、「お悔やみ全般」で用いても問題ありません。
知っているとためになるのしの豆知識
のしについてですが、元々は加工されているものではなく、本来は「薄く伸ばしたアワビを縁起物とした」ことが由来となり、今のようなのしの形となりました。
つまり、昔は「贈り物に薄く伸ばしたアワビを贈っていた」という習慣が、存在していたのです。
ですが、段々とアワビを贈る習慣が減っていき、その後は「似通ったもの(昆布、もしくは紙)」などで代用するケースが増えていったのです。
その後は、「印刷熨斗、折り熨斗」が一般的になり、現在のようなのしの文化が誕生しました。
また、のしはどのような場合でも用いたほうが良い・・・というわけではありません。
例えば、あまり気を許している相手ではない場合、「のしを付けない」ケースも存在します。
その場合は、のしなしで贈答品を贈ることもあるのですが、のしを使用している場合は「リボンを付けない」ということも大事です。
日本人は格好を気にするところもありますので、このようなマナーも守ってのしを活用するようになると、相手から喜ばれる贈答になるでしょう。
のしをあまり理解していない状況で贈答品を購入する場合ですが、そのことをショップの店員に伝えておくと、状況にあったのしを選択してくれるサービスも存在しますので、このようなサービスを有効活用することも大事です。