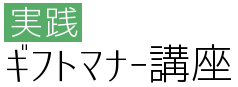ベストな断り方は「手紙」
相手から贈られてくるお中元やお歳暮を断りたいなと思っても、贈ってくれる相手の気持ちを考えるとなかなか断りづらいことはあるものです。
断る理由は多種多様で、相手側の理由で断る場合もあればこちら側の理由で断ることもあるでしょう。
どちらの場合でも、断り方は基本的に同じです。
断る際に最も大切なことは、そのタイミングです。
タイミングを間違えてしまうと、相手が失礼だと感じてしまったり、その後の人間関係にもマイナスの影響が出てしまうかもしれません。
そのため、タイミングには十分注意することが必要です。
それでは、どのタイミングで断るのがベストなのでしょうか。
相手の気持ちを考えながら角が立たない断り方をするなら、お中元やお歳暮を受け取った直後のタイミングをおすすめします。
時間があまり空いてしまうのはNGですが、受け取った翌日に断るというのも早すぎるのでNGです。
目安としては受け取ってから1週間~2週間ほどたったタイミングで、対面や電話などで伝えるのではなく手紙という方法で断るのがベストです。
角が立たない手紙の書き方
近年では手紙を書く人はとても少なくなりました。
しかしマナーという点においては、手紙はさまざまな局面で大活躍してくれるコミュニケーション手段です。
お中元やお歳暮のお断りをする際にも、手紙なら相手の気持ちを踏みにじることなく、また角を立てることなく断ることができます。
それでは、手紙を書く際にはどんな文面で書くのが良いのでしょうか。
言葉や表現の選び方次第で、相手が受ける印象は大きく変わります。
オリジナルの文章を考える必要はなく、定型文に沿ってそつなく断るのがスマートです。
綺麗な文字が書けなくて心配という場合、印刷したものを上からなぞるというのも一つの手です。
おすすめの文面としては、受け取ったお中元やお歳暮に対してのお礼を述べた上で「どうぞ今後はお気遣いなさりませんように」と添えれば、次回からはお断りしますという意図を相手に伝えることができます。
似たような文面としては、「お気持ちだけありがたく頂戴させていただきます」とか「御心配なさいませんようお願い申し上げます」なども良いでしょう。
あまりぼんやりとぼかし過ぎると相手へこちらの意図が伝わりづらいかもしれないという懸念はありますが、定型文を使えば、ぼんやりとした表現の中にもお断りしたいという気持ちを汲み取ってもらえます。
ちなみにリクエストや依頼を断る際には、相手に失礼にならないようきちんと理由を伝えることがマナーです。
しかし、お中元やお歳暮の受け取りをお断りするという場合には明確な理由がなくても問題ありません。
ただお断りしますと伝えるだけでも、気を悪くする人はそれほど多くはないでしょう。