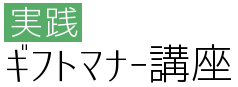十三祝い・十三参りとは何?
十三祝い・十三参りとは、もともと京都で行われていた伝統行事の一つで、13歳を迎えた子供の成長と健康を祝うイベントです。
13祝とも呼ばれていて、以前では発祥地である京都を中心に主に関西地方で行われてきました。
しかし近年では関東エリアにもこの行事が広がっています。
十三祝い・十三参りでは、寺社を参拝する際に13歳を迎える子供が大好きな漢字一文字が書かれた半紙を持参し、ご祈祷を受けます。
この漢字一文字は、できれば毛筆で元気いっぱいに書いたものがおすすめです。
ご祈祷を受けた後にはお守りとお供え物をいただいて寺社をあとにするのですが、境内を出るまでは振り返ってはいけません。
これには、授かったご利益を返すことがないようにという意味が込められています。
自社への参拝においては、七五三のように着物を着用する人もいるでしょう。
十三祝い・十三参りでは、子供は初めて大人用の着物に袖を通すのが一般的です。
ただし、着物でなければいけないというルールはないためスーツなどでもOKです。
十三祝い・十三参りのスーツを選ぶ際には、子供っぽいものではなく、大人の雰囲気が漂うデザインを選ぶと良いでしょう。
十三祝いと十三参りの由来と意味
十三祝い・十三参りには、13番目の菩薩様となる虚空蔵菩薩を参拝するという風習があります。
それによって、知恵と福徳を授かるのです。
もともとの由来は平安時代ごろまでさかのぼり、当時の浦和天皇が成人の儀を京都の嵐山で行ったことを起源としています。
成人の儀式を行ったのが法論寺だったため、そこから知恵と福徳を授かることが習わしとなったのでしょう。
当時は、13歳が成人だと考えられていました。
これまで健康に育ったことに対する感謝と、これからの健やかな人生への祈願という意味が、十三祝い・十三参りに込められています。
時期はいつがおすすめ?
十三祝い・十三参りの参拝時期は、旧暦で3月13日で、これは現在の4月13日となります。
しかしこの時期は子供は中学校に進学して忙しい時期ですし、学校がすでにスタートしているため、この日に参拝することは難しいでしょう。
そうした事情を考慮して、十三祝い・十三参りは3月から5月ぐらいの時期に参拝するのが良しだと考えられています。
4月に新学期が始まるということ、また5月のゴールデンウィークには気温が高くなって着物だと暑くなる点から、春休みに十三祝い・十三参りを行う家庭が多いです。
1月から3月の早生まれの子は、どのタイミングで十三祝い・十三参りするのがよいのでしょうか?
13歳というと、ちょうど小学校6年生を迎える年齢です。
早生まれの場合でもあえて1年ずらす必要はなく、小学校6年生に上がる前のタイミングで十三祝い・十三参りするのが良いでしょう。