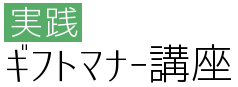世界各国で誰かが誰かのことを思って心づくしや感謝の気持ち、
また、愛情など様々な気持ちを込めて贈り物を贈るという制度があります。
もらう側になったときには、下さった人からの感謝の気持ちがこもっているので
とても温かい気持ちになることも多いといわれています。
世界各国で思いを込めて贈り物を贈る習慣というのは、いったいいつごろ誕生したのか気になりますが、
まずは日本ではどのような歴史をたどって現在のような様々な贈り物が誕生したのか、
大変気になったので調べてみました。
贈り物の歴史
そもそも贈り物というのは、日本では調べてみると縄文時代から存在していた風習のようです。
縄文時代というと、まだ稲作が完全に定着していないといわれている時代でした。
そのため、狩猟や採集などが盛んに行われ、食事などは森で取った木の実や動物を食べていたと言われています。
また、定住している人や定住していない人など様々な人々がいましたが、
基本的にはある程度、数家族程度の団体で住んでいたのではないかと言われています。
数家族単位で狩猟や採集に出かけると、どうしても獲物が少なかったり、
取ることができなかったという人も少なくなかったのではないかと推論されています。
そのため、食事の時にはすべての獲物を集団の中で分けて食していたのではないかと考えられます。
この食事の分配こそが贈り物の原始であり、日本人は昔から助け合って生活してきたのではないかという
仮説が成り立つと思われます。
正式な贈り物となったもの
時代が変わっていくにつれて、日本では農耕が盛んに行われるようになり、土地に定着し、
ムラという共同体が発生し、収穫などの感謝や来年も豊作でいられるようにという願いを込めて、
その年の作物を神にささげたといわれています。
そのため、神様をあがめる原始宗教が贈り物の原点であるという考え方もできるようですが、
wikipediaによると、(引用)「祭りの供物を神と祭祀に関わる者が共に食す神人共食思想があり、
それが祭りに参加する人々も含めた共食へ広がり、人々の間でやりとりされる贈答という習慣につながったとし、
また受け取った贈り物の一部を返す習俗は」ここからきているのではないかと言われています。
収穫祭から贈り物としての正式な習慣になったということを、考えている説が国内では定着しているそうです。
贈り物の内容
多くの人が送りあう風習である贈り物は、日本では食物が一番大きいと言われています。
その理由としては日本人の原始の収穫祭が根底にあると言われていますが、もともと日本人は食物の分配を
期限としているため、食物を提供しあうというのは人間同士の交流として最も定番であると考えられます。
また、食品ならばどんな人々でも喜んでくれるという非常に温かい心遣いであるといわれており、
日常的に贈りあってもそれほど心理的な負担とならないだろうという部分をもこめて、
贈りあっているのではないかと言われています。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E3%82%8A%E7%89%A9
http://www.kodai-bunmei.net/blog/2007/02/000133.html