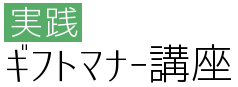夏の朝に涼し気な表情を見せてくれる朝顔の花言葉は?
朝顔といえば、夏の朝に花を咲かせ夕方になるとしぼむ性質があります。
朝に最も美しい表情を見せてくれるという所から、花の名前が「朝顔」とネーミングされました。
夏を代表する花の一つで、「朝の美人の顔」や「朝の容花」などとも呼ばれています。
朝顔には、紫や白、青など寒色系の色が多種多様です。
花の品種に共通する花言葉として「愛情」や「結束」がありますが、花の色ごとに花ことばは若干異なります。
例えば、白い花を咲かせる朝顔の花言葉は「あふれる喜び」とか「固い絆」です。
この絆というのは、朝顔のつるが支柱に絡みながら伸びていく姿に由来していると考えられます。
青い花の朝顔は、「はかない恋」「短い愛」という花言葉を持っています。
短いとか儚いというと、なんとなく悲しい雰囲気をイメージしてしまうかもしれません。
しかしこれらは、朝顔が持っている「朝しか花を咲かせてくれない」性質に由来しているものだと考えられています。
また朝顔には紫色の花もありますが、この色には「冷静」という花言葉があります。
ちなみに、朝顔を誕生花をする日もあります。
4月14日や7月6日など、必ずしも朝顔の開花時期や行事が行われる時期と重なっているわけではありませんが、この誕生日の人は朝顔に対してより大きな親しみを感じられそうです。
朝顔は日本の文化と大きな関係がある花
朝顔は、もともと中国から薬草として伝えられたと言われています。
奈良時代に詠まれた万葉集には、既に朝顔が登場しています。
この朝顔は秋の七草の由来となっていますが、実際には万葉集に登場する花は朝顔ではなく桔梗でないかという説も根強く残っています。
江戸時代には、朝顔のブームが何回か起こりました。
その際には、それまでは薬草をはじめとする食用だった朝顔の品種改良がおこなわれ、観賞するための花という位置づけへと変わっていきました。
八重咲タイプの花や花弁が細かく切れているものなど、現在でも珍しい品種が生み出されたのはこの時期だと考えられています。
こうした朝顔を披露するための祭りも、江戸時代に始まりました。
中でもよく知られているのは、東京都台東区で行われている入谷朝顔市ではないでしょうか。
もともとは朝顔を栽培していた農家が育てた朝顔を披露するために行われていた行事でしたが、現在では毎年7月6日から8日にかけて3日間だけ開催されています。
40万人ほどの観光客でにぎわうこの祭りには、120軒の朝顔業者に加え100軒以上の露店が立ち並び、盛大な祭りとなっています。
朝顔が持つ花言葉を頭に入れながら入谷朝顔市へ足を運べば、いつもとは違う気持ちで朝顔たちを楽しめるかもしれません。