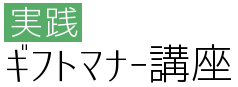ふくさとは?
結婚式などのお祝いごとがあるときには、ご祝儀を持っていくのが日本の昔からのしきたりです。
ご祝儀は袋のまま裸で持っていくのではなくて、ふくさ(袱紗)と呼ばれる布にくるんで持っていくのが礼儀です。
ふくさというのは元々は風呂敷の一種で、貴重品の入っている箱の上に掛けて使うものでした。
それがだんだんと現在の形に落ち着いてきて、冠婚葬祭などで使われるようになりました。
「広蓋」と呼ばれる黒塗りのお盆と一緒に使われるようになったのは比較的最近のことです。
ふくさには、ご祝儀袋を汚したり折り目がついたりしないようにするためという役割がある他、金封を受け取る相手の気持ちを思いやるという意味があります。
結婚式などの席でご祝儀袋をむき出しのまま先方に渡すのはマナー違反です。
どうしてもふくさがない時はハンカチで包んでも構いませんが、一つあれば重宝しますのでできるだけ購入するようにしたいものです。
ふくさのタイプと包み方
ふくさは小さな風呂敷程の大きさですが、「包むタイプ」のものと「挟むタイプ」の2種類があります。
包むタイプのふくさには、包みが開かないために爪が付いている「爪付きふくさ」や「台付きふくさ」などがあります。
台付きふくさには金封を乗せる台がついていますので、金封が型崩れしたりシワになったりしにくいというメリットがあります。
中には台の四隅にゴムやヒモが付いていて、金封がずれにくいような工夫がされているものもあります。
一方の挟むタイプは「金封ふくさ」と呼ばれており、長財布のような形をしています。
包むタイプと挟むタイプのどちらもマナーにはかなっていますが、特別に正式な場では包むタイプのふくさがおすすめです。
ふくさの種類
ふくさのほとんどはシルク製ですが、カラーバリエーションが豊富で、使い道によって最適な色が決まっています。
まず、お祝い事には赤やオレンジ、ローズピンク、ゴールド、薄紫などが適しています。
これに対してお悔やみの際にはグレーやグリーン、紺などが使われるのが普通です。
ですから、お祝い用の華やかな色とお悔やみ用の地味な色の両方のふくさを用意しておけばいいのですが、濃い紫色に関してはどちらの席でも使えますのでどれか一枚だけというのでしたら紫色がおすすめです。
これらは無地が普通ですが、お祝い用のふくさなら松竹梅や亀甲、扇などといったおめでたい柄の刺繍が入ったものも好んで使われています。
レースのあしらわれたものも最近人気が出てきています。
ふくさの包み方
包むタイプのふくさは、まず菱形になるように平面な場所に置きます。
この時、爪は右側に来るようにします。
ご祝儀袋は中心よりも少し左寄りにおいて包むのがコツです。